「限界利益」で予算のムダを見える化!
変動費と固定費の分解で、収益性改善の打ち手が明確に。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスして、実践ガイドを無料DL
原価計算は、製品やサービスを提供するためにかかった費用を算出し、適切な価格設定や利益の見通しを立てるために欠かせません。しかし、原価計算にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があることから、「計算方法が分からない」と悩むこともあるでしょう。計算方法は、自社の業態や目的に応じた選択が大切です。
この記事では、原価計算の主な種類と計算方法、計算手順について解説します。また、原価計算における課題と解決策、企業の利益向上に役立つ情報も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
原価計算とは

原価計算とは、製品やサービスの提供にかかる費用を把握し、分析するための手法のことです。企業が利益を確保しながら適切な価格を設定するためには、原価の正確な把握が欠かせません。
原価計算では、コストを分類した上で、それぞれの製品やサービスにどのように割り当てられるかを明確にします。また、原価計算にはいくつかの手法があり、目的に応じて使い分けられます。
原価計算とよく似た言葉に原価管理がありますが、原価管理は原価計算の結果を基にコストの削減や効率化を図る活動です。原価管理では、事前に目標となるコストを設定し、実際のコストと比較しながら改善策を講じます。
原価計算が「現状のコストを把握する手段」であるのに対し、原価管理は「コストを抑えるための管理活動」という点で異なります。
あなたの経営判断、「数字」に基づいていますか?
ROICや自己資本比率など、経営数字の分析方法を学ぶ実践ガイド!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
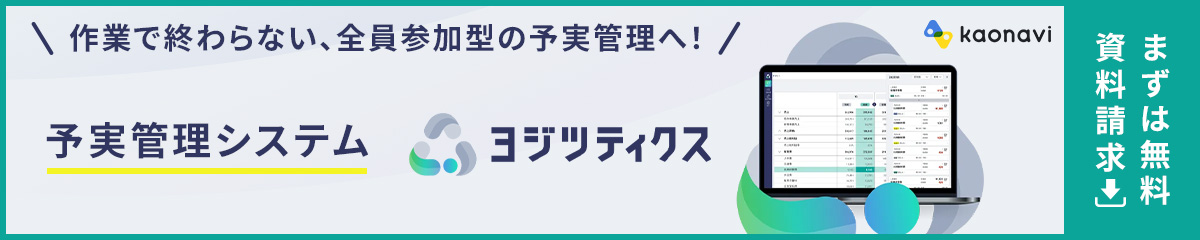 見積もり・デモのお問い合わせ
見積もり・デモのお問い合わせ原価計算の目的

原価計算の目的は、単にコストを計算するだけではありません。外部のステークホルダーに情報提供する「財務会計」、そして社内の経営管理のための「管理会計」としての目的があります。ここでは、財務会計と管理会計という2つの側面から、原価計算の目的について解説します。
財務会計
財務会計における原価計算の主な目的は、外部のステークホルダー(株主、投資家、税務機関など)に対して正確な財務情報を提供することです。企業は、製品やサービスの原価を算出し、それを会計帳簿に反映させることで、損益計算書や貸借対照表を作成します。
これにより、企業の収益性や経済的健全性を把握できるため、外部の評価や監査を受ける際に透明性が確保されます。財務会計は、税務申告や株主への報告など、企業の信頼性を高める上で欠かせません。
管理会計
管理会計における原価計算の目的は、企業の経営者や管理職が適切な意思決定をするための情報を提供することです。つまり「会社の利益を増やすにはどうすればよいか」を考えるための手がかりを与えてくれるのが管理会計の原価計算といえます。
例えば、「ある商品を作るのにどれくらいのコストがかかっているか」を正確に知ることで、販売価格を適切に設定したり無駄なコストを削減したりできます。また、「どの製品が最も利益を生んでいるのか」を分析し、経営資源をどこに集中させたらよいかを判断するのにも役立ちます。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
原価を構成する3つの要素
原価は、企業が製品やサービスを生産する際にかかる費用の総額を指し、主に以下の3つの要素で構成されます。
| 要素 | 説明 | 具体例(業種別) |
| 材料費 | 製品を作るために必要な原材料や部品のコスト | 自動車:鉄鋼、アルミ、ガラス、ゴム(タイヤ)、プラスチック(ダッシュボード) 食品:小麦粉、バター、砂糖、チョコレート、肉、野菜 アパレル:綿、ウール、シルク、生地の染料、ボタン、ジッパー 電子機器:半導体、液晶パネル、バッテリー、配線用の銅線 |
| 労務費 | 製造に関わる従業員の賃金や福利厚生費 | 製造業:工場作業員の給与、組立工の賃金、残業手当 飲食業:シェフや調理スタッフの給料、アルバイトの時給 建設業:現場作業員の賃金、大工の給与 IT業界:ソフトウェア開発者の報酬、エンジニアの人件費 |
| 経費 | 材料費・労務費以外の間接的なコスト | 製造業:工場の電気代、機械の減価償却費、検査費 飲食業:厨房機器の減価償却費、水道光熱費、テナントの賃料 建設業:建設機械のリース料、現場の安全管理費 小売業:店舗の家賃、POSシステムのメンテナンス費 |
これら3つの要素を把握することで、企業はより正確な原価計算ができ、コスト管理や価格設定の最適化を進められます。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
原価計算で重要な基本知識

原価には「材料費」「労務費」「経費」の3つの要素がありますが、そこからさらに「直接費」と「間接費」に細分化できます。また、原価計算においては、変動費と固定費に分ける考え方もあり、やや複雑です。ここでは、原価計算で押さえておきたい基本知識について解説します。
直接費と間接費
原価は大きく分けて「直接費」と「間接費」に分類されます。直接費とは、特定の製品やサービスに直接ひもづけられる費用のことです。例えば、製造業であれば以下のようなものが直接費に該当します。
- 直接材料費:製品の製造に使用する原材料や部品の費用
- 直接労務費:製造工程で実際に作業する職人やオペレーターの給与や手当
これらの費用は特定の製品単位ごとに計算できるため、比較的管理がしやすい特徴があります。一方、間接費とは特定の製品やサービスに直接ひもづけることが難しい費用のことです。具体的には以下のようなものが含まれます。
・工場の光熱費:複数の製品を製造する工場全体で発生する電気代や水道代
・間接労務費:製造現場の管理者や間接業務に従事するスタッフの給与
間接費は特定の製品に直接結びつけにくいため、「配賦」という手法を用いて分配します。配賦の方法には、作業時間や機械の稼働時間などに基づいて按分する方法があり、企業ごとに適した基準を設定することが重要です。
変動費と固定費
原価の考え方として、コストを「変動費」と「固定費」に分類する方法もあります。変動費とは、製品やサービスの生産量や提供量に応じて増減する費用のことです。
【変動費の例】
- 原材料費:製品の生産量が増えれば使用する原材料も増えるため、コストが変動する
- 販売手数料:売上に応じて発生する販売代理店や営業担当者への歩合制の報酬
- 輸送費:製品の出荷量が増えるほど、運送費用が増加する
変動費は売上と連動しやすく、利益率の計算にも影響を与えます。一方、固定費とは、生産量や売上の増減にかかわらず一定額発生する費用のことです。
【固定費の例】
- 賃借料:工場やオフィスの家賃は、生産量が増えても変わらない
- 人件費(固定給与):従業員の基本給は、生産量にかかわらず支払われる
- 減価償却費:設備や建物の購入費を長期にわたって分割計上する費用
固定費は一定額かかるため、売上が低迷すると利益を圧迫する要因になります。そのため、企業は固定費を抑えつつ、売上を伸ばす戦略を考える必要があります。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
原価計算の方法は主に6種類

原価計算には主に6種類の方法があり、それぞれの特性や適用場面が異なります。例えば、同じ製品を大量生産するのか、プロジェクト単位で生産するのかによって、計算方法を使い分けることがあります。業種や目的に応じて計算方法を選択しましょう。ここでは、6種類の原価計算の方法をそれぞれ解説します。
個別原価計算
個別原価計算とは、受注生産などのように製品や案件ごとに異なるコストを計算する方法です。例えば、造船や建設業、特注家具など、製品ごとにコストが大きく異なる業種で用いられます。
コスト管理が細かくできる利点がある一方で、管理負担が大きくなる点に注意が必要です。計算方法は複数のプロセスを踏むため複雑ですが、簡単にまとめると以下の3つの手順で計算します。
- 原価を費用別で集計する
- 部門別に振り分ける
- プロジェクト別で振り分ける
総合原価計算
総合原価計算は、大量生産される製品の原価を計算する際に用いられる方法です。食品・化学・繊維など、同一の製品を大量に生産する業種に適しています。
この計算方法では、一定期間内の総コストを全体の生産量で割ることで、1単位あたりの原価を求めます。個別原価計算とは異なり、製品ごとの細かいコスト把握は難しいものの、簡単に原価を求められる点がメリットです。
部分原価計算(直接原価計算)
部分原価計算(直接原価計算)とは、固定費を考慮せずに、変動費のみを製品の原価として計算する手法です。管理会計の分野でよく用いられ、短期的な意思決定に役立ちます。固定費を別に管理するため、損益分岐点の分析や、製品ごとの利益貢献度を評価しやすいというメリットがあります。
損益分岐点とは、企業の売上がちょうど費用と一致し、利益も損失も発生しないポイントのことです。部分原価計算では、変動費と固定費を分けて考えるため、企業が黒字化するために必要な売上を明確に把握できます。
全部原価計算
全部原価計算は、製品の原価に変動費だけでなく固定費も含めて計算する方法です。財務会計で一般的に使用され、企業の損益計算書や貸借対照表に反映されます。
この方法は、全てのコストを含めた正確な原価を算出できるため、財務報告や税務申告に適しています。ただし、短期的な意思決定には向かず、価格設定の柔軟性が低くなる可能性があります。
標準原価計算
標準原価計算とは、あらかじめ設定した標準的なコストを基に原価を計算し、実際の原価との差異を分析する方法です。製造業で広く活用され、コスト管理や改善活動に役立ちます。
この方法を用いることで、無駄なコストを特定し、改善に向けた活動がしやすくなります。しかし、標準原価の設定が不適切だと、正しいコスト管理が難しくなる点に注意が必要です。
実際原価計算
実際原価計算とは、発生した費用を全て記録し、製品ごとの正確な原価を計算する方法のことです。個別原価計算や総合原価計算と組み合わせて用いられます。
この方法の利点は、実際のコストを正確に把握できる点にあります。ただし、変動要因が多いため、計算が複雑になりやすく、リアルタイムでの管理が難しいことが課題といえます。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
原価計算の手順
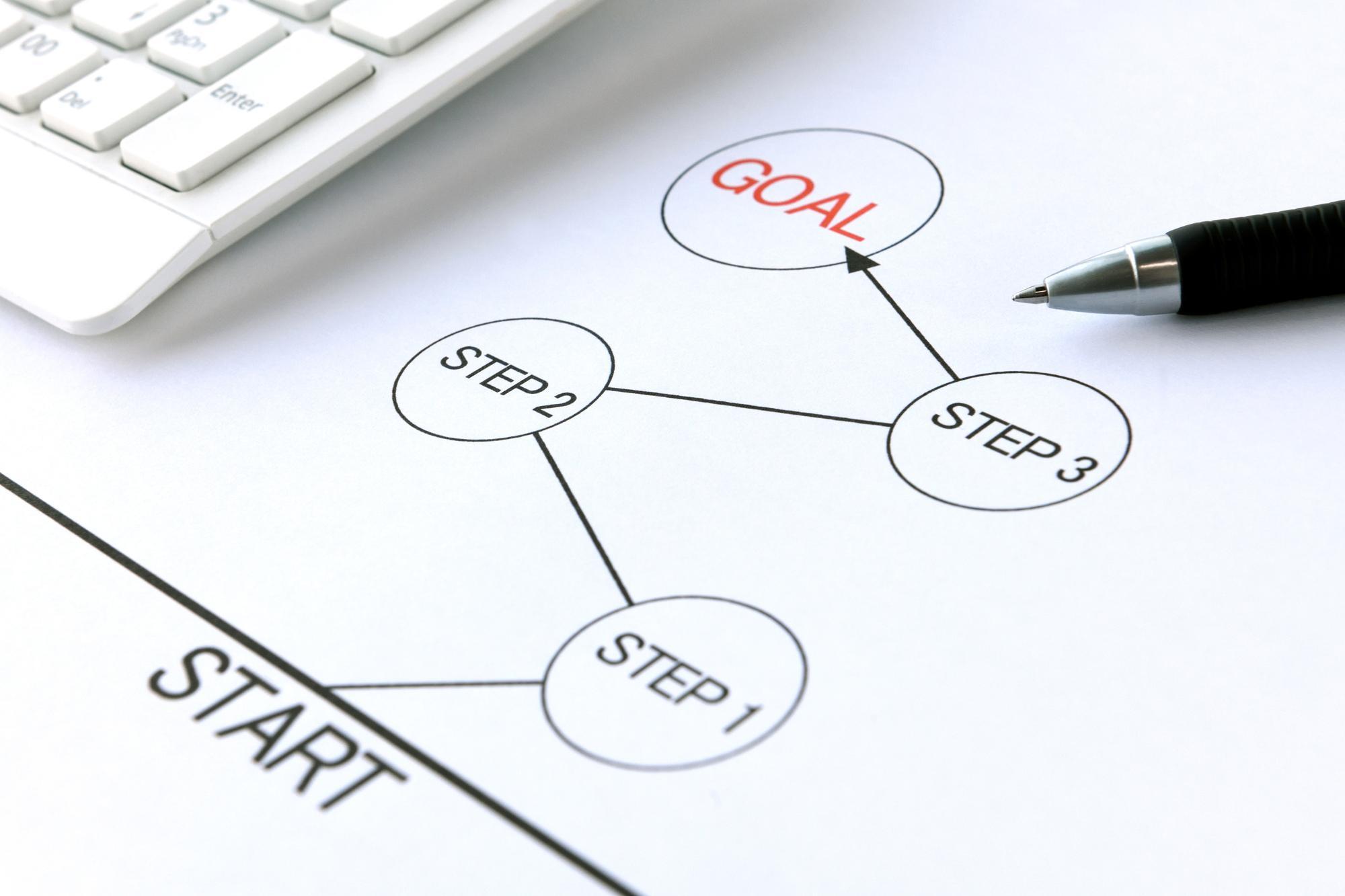
原価計算にはいくつか種類があり、それぞれで計算の流れも異なります。ここでは、受注生産やプロジェクト型ビジネスで主に活用される、個別原価計算の手順について解説します。なお、ここで紹介する手順はあくまでも一例であり、企業によって異なる場合もある点にご留意ください。
1.費目別原価計算
まずは、製品やサービスを作る際に発生するコストを「材料費」「労務費」「経費」の3つの費目に分類して計算します。それぞれ、直接費と間接費に分けて集計しましょう。この分類によって、どの部分にどれだけのコストがかかっているのかが明確になり、コスト削減のポイントを把握しやすくなります。
2.部門別原価計算
費目別原価計算で求めた間接費(直接的に製品に関わらない費用)を各部門に配賦し、部門ごとの実際のコストを明確にします。間接費をどのように配賦するかは、配賦基準に基づきます。以下は、配賦基準の例です。
- 材料費:各部門が使用した材料の量に基づいて配賦
- 光熱費:各部門の専有面積に基づいて配賦
- 労務費:各部門での労働時間に基づいて配賦
3.プロジェクト(製品)別原価計算
最後に、費目別原価計算で算出した直接費と、部門別原価計算で算出した間接費を合計して、最終的にプロジェクト(製品)ごとの原価を算出します。このステップで、企業はどのプロジェクト(製品)がどれだけのコストをかけているかを把握でき、利益率の改善や製品ラインの最適化に役立ちます。
現場と経営の目線が合った予実管理へ!
標準化と仕組み化で叶う、経営を強くする仕組みとは?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
原価計算における課題

原価計算は企業が利益を上げるために必要不可欠な作業ですが、いくつかの問題点があります。これらの課題を理解し、適切に対策を講じることが、適切な価格設定や経営判断につながります。以下で紹介する4つの課題を把握しておきましょう。
計算が複雑かつ工数が多い
原価計算は多岐にわたる要素を考慮する必要があり、複雑です。直接材料費、直接労務費、間接費などの各項目を正確に集計し、それぞれの配分方法を決定する必要があります。
特に原価計算を手動で進める場合、多くの時間と労力を要し、正確性を保つことが難しくなります。さらに、各部署からのデータ収集や集計作業にも手間がかかり、原価計算のために膨大な工数がかかることが大きな課題です。効率的に計算を進めるためには、ITツールの導入を検討するとよいでしょう。
ヒューマンエラーが生じやすい
原価計算は複雑であるため、手作業による計算やデータ入力ではミスが発生しやすくなります。数字の入力ミスや計算式の誤り、不正なデータの混入などが原因で、誤った原価情報が算出される可能性があります。
このような誤りが経営判断に影響を与えると、予算オーバーや過少な原価見積もりが発生し、結果的に経営資源が無駄に使われることにもつながりかねません。ヒューマンエラーを防ぐためには、ダブルチェックや自動化ツールの導入が必要です。
属人化しやすい
原価計算は専門的な知識やノウハウが必要なため、その業務が特定の担当者に依存してしまうリスクがあります。特に表計算ソフトなどの手動ツールで計算している場合、担当者のスキルや経験に大きく頼ることになります。
その結果、担当者が退職したり休職したりすると計算が滞り、他の担当者が業務を引き継ぐことが困難になるでしょう。属人化を防ぐためには、業務フローを標準化し、誰でも扱えるような仕組みを整えることが重要です。
部門間での情報共有が難しい
原価計算には製造部門、経理部門、経営層など複数の部門が関与します。これらの部門が関わるデータを円滑に共有し協力することは重要です。情報共有が不足すると、原価の正確な把握が困難になりかねません。
例えば、製造部門が正確なデータを経理部門に提供しない場合、経理部門は誤った情報を基に原価計算をしてしまうでしょう。さらに、経営層が原価計算の進捗を把握していないと、適切な意思決定が遅れることにもつながります。部門間での情報共有を促進するために、統一されたシステムを使うなどの工夫が必要です。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
企業の利益向上には予実管理システムの導入もおすすめ

企業の利益を上げるためには、費用対効果を常に意識した経営が欠かせません。予算と実際のコストのズレを素早く把握し、その原因を分析することが重要です。予実管理システムを導入すれば、実際のコスト(実際原価)と予算(標準原価)とのギャップを比較・分析できます。ここでは、予実管理システムを導入するメリットについて解説します。
予算と実際のコストのギャップを可視化できる
予実管理システムを導入すれば、標準原価(計画原価)と実際にかかった原価(実際原価)を簡単に比較できます。原価計算を通じて、「どの部分でコストが予算を超過したのか」「予算内で収まったのか」を迅速に把握できます。
コスト増加の原因を分析して対策ができる
予実管理システムでは、予算に対する実際のコストを細かくトラッキングでき、どの項目でコストが増加したのかを正確に分析できます。例えば、原材料費や人件費、輸送費など、費用項目ごとの変動を把握でき、特定の要因によるコスト増加を明らかにできます。
ゆえに、コストが増加した原因を特定し、無駄な支出を減らすための具体的な対策を講じることが可能です。
経営判断の精度が向上する
予実管理システムにより、企業は常に正確で最新のコストデータを取得できます。このデータを基に、経営者は迅速かつ的確に意思決定を進められるようになり、経営判断の精度が向上します。データに裏づけられた意思決定は、企業のリスク管理や利益最大化につながります。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
予実管理システムなら「ヨジツティクス」
ヨジツティクスは、予算(標準原価)と実績(実際原価)を簡単に比較できる予実管理システムです。予算と実績の差異をリアルタイムで把握できるため、問題点や無駄な支出を迅速に発見し、改善策を打ち出すことが可能です。
さらに、データ分析も簡単に実行でき、経営層や担当者は正確な情報を基に迅速かつ効果的な意思決定を行えます。ユーザーフレンドリーなインターフェースであり、マニュアル不要で誰でも簡単に操作できる点も魅力です。コストの予算超過を防ぎ、効率的なリソース管理を実現したい企業は、ぜひご利用ください。
現場と経営の目線が合った予実管理へ!
標準化と仕組み化で叶う、経営を強くする仕組みとは?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
まとめ

原価計算は、企業の利益向上にとって欠かせないプロセスであり、適切なコスト管理のためにも計算方法を理解することが大切です。
しかし、原価計算の方法はいくつかあり手順も複雑であるため、属人化しやすかったりヒューマンエラーが生じやすかったりといった課題があります。こういった課題を解決するには、ITツールの活用が有効です。
また、コスト管理の面では、予実管理システムの導入もおすすめです。予算と実績の差異をリアルタイムで把握することで、コストの変動要因を分析し、無駄なコストの削減や収益性の向上につなげられます。
予実管理システムの「ヨジツティクス」では、経営企画のスペシャリストが運用面まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひご利用ください。
【利益は出ているのに、資金が増えない理由とは?】
それキャッシュフローを見逃しているせいかもしれません。
●現金の動きが見える「C/F」
●成長余力を示す「FCF」
●手元資金の“使える額”を正しく把握

