「限界利益」で予算のムダを見える化!
変動費と固定費の分解で、収益性改善の打ち手が明確に。
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスして、実践ガイドを無料DL
企業の財務諸表を読む上で避けて通れないのが「繰延税金資産」です。繰延税金資産の仕組みは複雑なことから、理解するのが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。繰延税金資産は、適切に管理しなければ財務リスクにつながる可能性もあります。
この記事では、繰延税金資産の概要や、仕訳方法について分かりやすく解説します。また、記事の後半では、回収見込みの見極めに役立つ予実管理システムについても紹介しているため、経営改善や業務効率化を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
繰延税金資産とは

企業の会計処理と税務処理の間には、ズレが生じることも少なくありません。会計上は費用として記録できても、税務上は認められない場合や、その逆のケースもあります。このようなズレは、将来の税金の支払いに影響を与える可能性があります。
そこで登場するのが「繰延税金資産」です。ここでは、繰延税金資産の意味や、似た言葉である「繰延税金負債」「繰延資産」との違いについて解説します。
税務会計と企業会計のズレを調整する仕組み
会計上の利益と税務上の利益の差異を調整するために計上する資産のひとつが「繰延税金資産」です。これは、会計上の損失や特定の費用が税務上の損金として認められず、将来的に税負担が軽減されることを見込んで記録されるものです。
例えば、ITの開発費など高額な費用は税務上では減価償却費として数年かけて少しずつ費用を計上しますが、会計上では保守的に一括で費用計上する場合があります。このようなケースでは、将来的に税務上の控除が受けられる分の税金を先に払っているとみなし、現時点での会計処理において「繰延税金資産」として記録します。
繰延税金負債や繰延資産との違い
「繰延税金負債」も会計と税務のズレを調整する税効果会計です。繰延税金資産とは反対に、将来的に税負担が増加することが見込まれる場合に計上されます。
「繰延資産」は企業が支出した費用のうち、将来的に利益を生むと考えられる資産として記録する項目です。例えば、開業費や開発費などが該当します。繰延資産は一括費用計上せず、複数年にわたって償却する形で徐々に費用化されます。
あなたの経営判断、「数字」に基づいていますか?
ROICや自己資本比率など、経営数字の分析方法を学ぶ実践ガイド!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
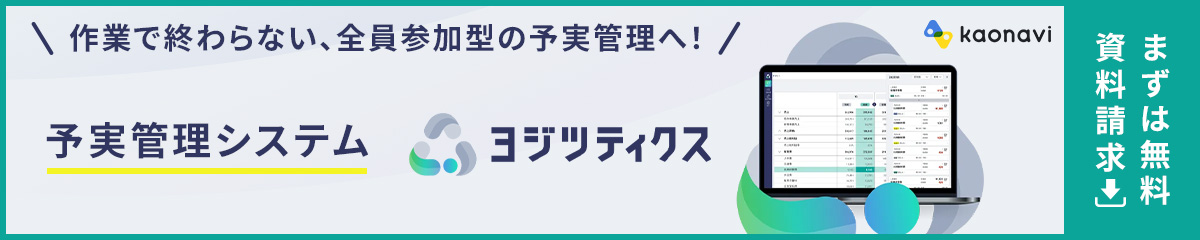 見積もり・デモのお問い合わせ
見積もり・デモのお問い合わせ繰延税金資産の計上要件

繰延税金資産の計上に際しては、慎重に見極める必要があります。なぜなら、企業の将来の業績や経営環境によって、将来の税金負担が軽減されるかどうかが変わってくるためです。そこで重要になるのが、計上要件である「回収可能性」です。ここで詳しく説明します。
繰延税金資産の回収可能性
将来の税金負担を軽減できるだけの十分な利益があるかどうかの見込みを評価するものが、回収可能性です。企業会計基準委員会の指針によると、以下の3つの要件に基づいて回収の見込みがあるかを見極めます。
| 1.収益力による判断 | 将来的に利益(課税所得)が出る見込みがあるかを確認する。具体的には、過去の業績や納税状況、今後の業績予測を考慮し、税務上の繰越欠損金や一時差異が回収できるか判断する |
| 2.タックス・プランニングによる判断 | 会社が税負担を減らすために、含み益のある資産を売却するなどの計画があるかを確認する。これにより将来的に課税所得が発生し、繰延税金資産の回収の可能性があるかどうかを判断する |
| 3.将来加算一時差異による判断 | 将来のタイミングで発生する税務上の調整(加算一時差異)が、繰延税金資産の回収につながるかを確認する。例えば、繰越欠損金と相殺できるかどうかを見極める |
簡単にまとめると、「将来の利益」「税金対策の計画」「税務上の調整」の3つを考慮して、回収できる可能性を見極めます。
(参考: 『企業会計基準適用指針第 26 号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針果/企業会計基準委員会』)
回収可能性における企業分類表
企業は以下5つのいずれかに分けられ、それぞれの分類に応じて回収の見込みが評価されます。
| 分類 | 企業の状況 | 回収可能性の判断基準 |
| 分類1 | 過去3年および当期において、将来減算一時差異を大幅に上回る課税所得があり、近い将来、経営環境の著しい変化が期待できない企業 |
|
| 分類2 | 過去3年および当期において、課税所得は将来減算一時差異を下回るものの安定的に発生しており、近い将来に営業環境に著しい変化が見込まれず、重要な税務上の欠損金がない企業 |
|
| 分類3 | 過去3年および当期において、課税所得が大きく変動しているものの、重要な税務上の欠損金がない企業 |
|
| 分類4 | 以下のいずれかの条件に当てはまり、かつ翌期で一時差異等加減算前課税所得が発生すると見込まれる企業
①過去3年間または当期において、重要な税務上の欠損金が発生している |
|
| 分類5 | 過去3年および当期において重要な税務上の欠損金が発生しており、翌期も同様の見込みである企業 |
|
なお、各分類の要件をいずれも満たさない企業は、分類1~5の要件で乖離(かいり)の度合いが最も小さいものに分類されます。
「重要な税務上の欠損金」とは、企業の経営状況に重要な影響を与える可能性のある多額の税務上の欠損金を指しますが、具体的な判断基準はありません。「スケジューリングできない将来減算一時差異」とは、税務上の損金算入時期が個別に特定できない将来減算一時差異を指します。
(参考: 『企業会計基準適用指針第 26 号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針果/企業会計基準委員会』)
回収可能性がなくなった場合は「取り崩し」

繰延税金資産の回収の見込みは、企業の業績や経営環境によって変動します。万が一、回収に期待できなくなった場合には、「取り崩し」という会計処理が必要です。ここでは、取り崩しの意味や影響について解説します。
繰延税金資産の取り崩しとは
取り崩しとは、企業が計上していた繰延税金資産が、将来的に回収できないと決めた場合に、その資産を帳簿から取り除く会計処理のことです。
繰延税金資産は、将来的な課税所得の減少を見込んで記録されるものですが、経営環境の変化や業績の悪化により、見込んでいた課税所得が発生しない可能性が出てくると、その資産価値が低下します。
例えば、長期間にわたり赤字が続く場合は会計基準に基づいて「回収に期待できない」と判断し、取り崩しを実行して当期の損益計算書に影響を与える形で処理する必要があります。
取り崩しによる影響
会計処理では、取り崩した分が費用として計上されるため、実質的な利益が減少します。 少額であれば影響は限定的ですが、多額の取り崩しが発生すると高額赤字となるケースもあります。
例えば、企業の実際の損失が1億円だった場合でも、取り崩しによって100億円の損失が計上されると、最終的な純損失は101億円です。繰延税金資産の見直しによる下方修正が行われた場合、企業の財務状況に深刻な影響を与えることがあるため注意が必要です。
繰延税金資産の具体的な計算方法

繰延税金資産は、将来減算一時差異の合計額に法定実効税率を乗じて算出します。ゆえに、「将来減算一時差異の把握」「法定実効税率の確認」という2段階のステップを踏んで、ようやく計算できます。以下で紹介する3つの手順に従って算出してみましょう。
STEP1.将来減算一時差異の把握
将来減算一時差異とは、会計上の利益と税務上の所得との間に生じる一時的な差異のうち、将来的に税務上の利益を減少させる効果を持つものを指します。例えば、貸倒引当金や減価償却費の損金不算入額などが該当します。
将来減算一時差異と似た言葉に「永久差異」があります。永久差異は、将来においても解消されることがなく、会計上と税務上の所得に恒久的なズレを生じさせるものです。
代表的な例としては、法人税法上損金算入が認められない交際費や、受取配当金の益金不算入額などがあります。永久差異は税務計算には影響しないため、繰延税金資産の計算対象とはならない点に注意しましょう。
STEP2.法定実効税率の確認
法定実効税率とは、企業の利益に対して課される税金の割合のことです。日本における法人税率は単独ではなく、法人税、住民税、事業税などを含めた総合的な税率として計算されます。法定実効税率は以下の式で求められます。
法定実効税率=[法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率]÷(1+事業税率)
法定実効税率は、税制改正などによって変動する可能性があるため、最新の税率を確認することが大切です。
STEP3.繰延税金資産の計算
将来減算一時差異と法定実効税率が明らかになった後は、以下の計算式に当てはめて算出します。
繰延税金資産=将来減算一時差異×法定実効税率
例えば、貸倒引当金が3,000万円、賞与引当金が5,000万円、棚卸資産評価損否認額が2,000万円で、将来減算一時差異として1億円を計上したとします。そして、法定実効税率が30%の場合は、以下のように計算します。
1億円×30%= 3,000万円
この計算によって、企業は税務上の控除可能な金額を見積もることができ、財務戦略の一環として活用できます。
【例あり】繰延税金資産の仕訳方法

繰延税金資産の仕訳では、「法人税等調整額」という勘定科目を使用します。法人税等調整額とは、企業の財務諸表で計上された税金の額と、実際に支払う法人税の額との間に生じた差異を調整するための金額です。ここでは、仕訳方法を具体的な例を交えて解説します。
仕訳例:貸倒引当金
貸倒引当金は、将来の貸倒れに備えて計上されますが、税務上ではその計上が認められない場合があります。
例えば、企業が会計上で500万円の貸倒引当金を計上したものの、税務上では損金として認められなかった場合、「繰延税金資産」が発生します。この仕訳のポイントは、税務上で認められなかった部分に対して税金を繰延べることです。
【仕訳例:計上時】
法定実効税率30%の場合の計算式は以下のとおりです。
計算式:500万円(貸倒引当金)×30%(法定実効税率)=150万円
この場合の繰延税金資産は、以下のように仕訳けます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 繰延税金資産 | 150万円 | 法人税等調整額 | 150万円 |
【仕訳例:解消時】
将来的に税務上で損金として認められた場合、繰延税金資産は解消され、税金が反映されます。例えば、「翌期、貸倒損失が発生し、貸倒引当金が解消された」といったケースです。繰延税金資産が解消された際には、以下のように仕訳けます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 法人税等調整額 | 150万円 | 繰延税金資産 | 150万円 |
仕訳例:賞与引当金
賞与引当金は、企業が従業員に支払う賞与に備えて計上される引当金であり、会計上では計上されても、税務上では支払いが確定するまで損金として認められないことが多くあります。この場合も、繰延税金資産が発生し、将来の税負担を調整する必要があります。
以下は、会計上、賞与引当金300万円を計上したものの、税務上は損金として認められなかった仕訳例です。
【仕訳例:計上時】
計算式: 300万円(賞与引当金)×30%(法定実効税率)= 90万円
※法定実効税率30%の場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 繰延税金資産 | 90万円 | 法人税等調整額 | 90万円 |
【仕訳例:解消時】
賞与が支払われ、税務上で損金として認められた場合、繰延税金資産は解消されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 法人税等調整額 | 90万円 | 繰延税金資産 | 90万円 |
現場と経営の目線が合った予実管理へ!
標準化と仕組み化で叶う、経営を強くする仕組みとは?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
繰延税金資産における注意点

税法の改正や経済状況の変動など、さまざまな要因が回収の見込みに影響を与えるため、常に最新の情報を把握し、適切な決断を下すことが求められます。ここでは、繰延税金資産を取り扱う上で注意したい2つのポイントを紹介します。
税法の改正によって回収可能性が変動する可能性がある
繰延税金資産の計算には、税法や会計基準が大きく影響します。例えば、税法の改正により、税金の控除対象が変更されたり、税率が見直されたりすることがあります。
税率や課税ルールが変わることで、過去に計上した繰延税金資産が無効になる可能性も少なくありません。企業は定期的に税法改正に注目し、それに対応することが大切です。
回収可能性の判断は慎重に行う
繰延税金資産は、将来の課税所得によって回収できる見込みがある場合にのみ計上できます。ゆえに、回収見込みの見極めは、企業の過去の業績や将来の事業計画、経営環境などを考慮して慎重に行う必要があります。
特に、過去に赤字が続いた場合や業績が不安定な場合には、繰延税金資産の計上を慎重に検討したほうがよいでしょう。
煩雑なファイル管理から脱却し、予実管理を一元化。
最新の数値をリアルタイムで把握できる、予実管理設計ガイド。
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
回収可能性の判断に予実管理システムが役立つ

回収の見込みを見極めるためにも、将来の課税所得を正確に予測することが重要です。しかし、将来の予測は不確実性が高く、企業の業績や経営環境の変化によって大きく変動する可能性があります。そこで、役立つのが予実管理システムです。
予実管理システムとは、企業の予算(予算計画)と実績(実際の収支)を比較・分析するためのシステムのことです。予実管理システムを活用すれば、より精度の高い将来予測が可能となり、回収見込みの判断精度を向上させられます。ここでは、予実管理システムを導入するメリットについて解説します。
精度の高い将来予測
予実管理システムを活用して、過去のデータと実績を基に将来の財務状況を予測すれば、将来の課税所得をより正確に見積もれます。
繰延税金資産における回収の見込みは、将来の課税所得に大きく依存するため、今後の税務状況を明確に予測することが大切です。予実管理システムは過去の実績データをいつでも確認できることから、回収されるかどうかを判断する際の精度が向上します。
経営判断の精度向上
予実管理システムは、企業の実績と予算との差異をリアルタイムで把握できます。予算と実績の差異を分析することで、経営者は早期に問題を発見し、将来の予測を柔軟に調整できるでしょう。
例えば、売上が予算を下回っている場合には、その原因を分析・特定し、販売戦略の見直しやコスト削減などの対策を講じることが可能です。
リスク管理の強化
予実管理システムを通じて、税務関連のリスクを早期に特定し、回収の見込みに影響を与える要因を予測することも可能です。
予算と実績に大きな差異があった際に、市場の変動、競合の動向、為替レートの変動など、将来予測に影響を与える可能性のある要因を早期に特定することで、リスクを軽減できます。早期に対策を講じれば、回収見込みの判断における不確実性を減らせます。
会社の「体力」は、B/Sを見ればわかる。
自己資本比率・流動比率から、経営の安定性とリスクを見抜く!
⇒ PDFを無料DL|【公式】https://www.kaonavi.jp
予実管理を効率化するなら「ヨジツティクス」
予実管理において、「予算策定や見込みの精度が低い」「データ収集や入力に手間がかかる」といったお悩みを抱えている場合は、予実管理システムの「ヨジツティクス」がおすすめです。
ヨジツティクスは、リアルタイムで予算と実績を自動的に把握・分析し、迅速な意思決定を支援します。過去のデータを基に将来予測を立て、課題を早期に発見することで、経営の安定化を実現できます。
また、シンプルで使いやすいインターフェースになっており、マニュアルを読まなくても操作可能です。従業員の負担を軽減し、業務の効率化を進められます。経営企画のスペシャリストとサポートデスクが導入から運用まで丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
経営数字が読めると、議論の質が変わる。
財務3表のつながりと数字の「意味」を捉える力が身につく実践ガイド。
⇒ 【無料DL】https://www.kaonavi.jp
まとめ

繰延税金資産は、将来の税負担を軽減できる会計上の資産ですが、適切な会計処理と回収見込みの見極めが重要です。回収の見込みを見極めるには、将来の課税所得の見積もりや財務状況の分析が欠かせません。
しかし、将来の予測は不確実性が高く、企業の業績や経営環境の変化によって大きく変動する可能性があります。予実管理システム「ヨジツティクス」を活用すれば、より精度の高い将来予測が可能となり、繰延税金資産の回収可能性の判断精度を向上させることが可能です。
また、予算と実績の差異をリアルタイムで確認でき、迅速な経営判断にもつながります。クラウド型のシステムで、場所や時間を問わず、関係者間で情報を共有できる点もメリットです。
【予実管理の精度を向上させるには?】
多くの企業が抱える運用負担を解消し、 経営の意思決定をサポートする実践ガイド。
●予算・実績・見込みを自動集計でデータを一元管理
●誰でも使える設計だから運用の標準化が進む
●全員がいつでも最新の数字を共有できる状態へ

